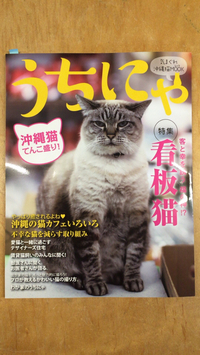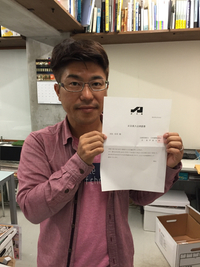2011年06月13日
中学校PTA活動「朝の語り」行って来ました!
今朝、中学校のPTA活動である「朝の語り」を1クラス担当してきました。

毎週月曜日に行われる職員会議中の時間帯、学生たちが教室でフリーになって落ち着かないようになってしまうので、その時間をPTAで有効に使っていこうという活動です。
保護者や地域の人たちで交代で、各1クラスづつ担当する活動です。
私は、月1回くらいのペースということになっています。
この活動は、結構前から、続いているようです。
私は、今年から長男が中学生になったばかりですので、初めたばかりです。
話す内容は、各個人に任せられております。
実は、これが一番難しい・・・

昨日、急遽依頼を受け、何を話すか決まらないまま教室に向かいました。

そして、みんなを前にして突然浮かんできたのは、学問の話。
最初に「勉強好きな人!」・・・・誰もてを挙げません・・・予想通り。

続けて、「勉強嫌いなひと!」・・・すると直ぐに多くの子たちが反応して手を挙げてくれました。

素直に反応してくれる子どもたちをみて、なぜか一安心してしましました。

そこで、今朝は、数学の楽しさを話してみることに!

言葉も存在しなかった時代からどうやって、数字が生まれてきたのだろうか?
そして、数字が宗教だった時代のお話。
そして、コンピューターって何で動いているの?
「光って、一体何者?」って、こんなこと考えたことある?
と身の廻りにある当たり前のことが、実は、当たり前すぎて不思議にも思っていなかったことを話してみました。
今、学生たちが習っている当たり前の公式や定理・理論などは、実は、好奇心の中から生まれてきたんだということを話しました。
時間も短いので解説までは行いませんでしたが、みんな「言われてみればぁぁ」という顔をしていましたね。

最後は、チャイムがなったので、慌てて

「空間が歪むって、話もあるよ。」
「透明マントは、本当にあるよ。」
と昔のドリフの「8時だよ・・」みたいに言葉を連発して終わりました。

意外と、受け答えの出来る反応があったので良かったと思います。
駆け足ではありましたが、学問は楽しむことも出来るということを少しでも感じてもらえたらいいなぁと思いました。
昨日の突然の依頼だったので、行き当たりばったりの話になってしまいましたが・・・・

建築の話をしたら止まりそうもないし・・・

日頃、ネタを整理しておかないといけませんね。

↓1日1回クリックして頂けるだけで今後の励みになります。

にほんブログ村
Posted by Shingo at 21:13
│プライベート
この記事へのコメント
こんにちは。
お疲れさまでした。
僕も、よく、同じ質問を、高校生に投げかけま~す。
勉強が嫌いなひと~
僕も、一緒に、手を挙げます。
なぜなら、それが正解だからです。
「勉強」の「勉」は、「つとめて」という意味。
「強」は「強制」ですから、強制されて好きになるなんて、よほどのSM趣味の人だけです。
ところが、
別に「学び」「学習」「学問」「研究」という言葉があって、
これらには、強制の意味はありません。
それなのに、勉強という言葉を、みんな使いすぎるんです。
そもそも、
小学校から高校までの学校では、
人を殺してはいけないとか、嘘をついてはいけないといったことはじめ、
強制的に教え込むことが中心に、教育されます。
したがって、決まった答えを出す練習が、多いのです。
一方、
例えば大学は、専門分野を研究する場なので、楽しいわけです。
1+1=2というのを、学校では教え、
1+1が2でない場合を、大学からは研究する、
つまり、答えがないことを研究するのだから、面白くてやめられません。
僕たち教育者は、
日頃からネタを考えて、頭のポケットや引き出しに、整理して入れておきます。
そして、もっとも、有効な時に有効なネタを出します。
ポケットや引き出しが多い先生に、上手に教えるのがうまい人が多いのです。
口先だけの教育者は、楽しませるだけで、教育してないから駄目で、
頭のポケットや引き出しが多いほど、よい先生とされます。
ただそれは、プロだから当たり前で、
Shingoさんは、
我々教育者が、つい落としがちだったり、忘れがちなことを、
ご自分の好きなように、話せばいいんです。
ですから、次回は、
話をしたら止まりそうもない、建築や建築に関する話を、
時間内に収まるように、話すのが、いいのです。
なぜなら、建築家にしか語れないことを話すことこそ、意味があるのです。
先生では、無理なんですから。
ただし、ネタは、
必ず子ども達にあう形に変形し、脚色して、使うといいです。
では。
お疲れさまでした。
僕も、よく、同じ質問を、高校生に投げかけま~す。
勉強が嫌いなひと~
僕も、一緒に、手を挙げます。
なぜなら、それが正解だからです。
「勉強」の「勉」は、「つとめて」という意味。
「強」は「強制」ですから、強制されて好きになるなんて、よほどのSM趣味の人だけです。
ところが、
別に「学び」「学習」「学問」「研究」という言葉があって、
これらには、強制の意味はありません。
それなのに、勉強という言葉を、みんな使いすぎるんです。
そもそも、
小学校から高校までの学校では、
人を殺してはいけないとか、嘘をついてはいけないといったことはじめ、
強制的に教え込むことが中心に、教育されます。
したがって、決まった答えを出す練習が、多いのです。
一方、
例えば大学は、専門分野を研究する場なので、楽しいわけです。
1+1=2というのを、学校では教え、
1+1が2でない場合を、大学からは研究する、
つまり、答えがないことを研究するのだから、面白くてやめられません。
僕たち教育者は、
日頃からネタを考えて、頭のポケットや引き出しに、整理して入れておきます。
そして、もっとも、有効な時に有効なネタを出します。
ポケットや引き出しが多い先生に、上手に教えるのがうまい人が多いのです。
口先だけの教育者は、楽しませるだけで、教育してないから駄目で、
頭のポケットや引き出しが多いほど、よい先生とされます。
ただそれは、プロだから当たり前で、
Shingoさんは、
我々教育者が、つい落としがちだったり、忘れがちなことを、
ご自分の好きなように、話せばいいんです。
ですから、次回は、
話をしたら止まりそうもない、建築や建築に関する話を、
時間内に収まるように、話すのが、いいのです。
なぜなら、建築家にしか語れないことを話すことこそ、意味があるのです。
先生では、無理なんですから。
ただし、ネタは、
必ず子ども達にあう形に変形し、脚色して、使うといいです。
では。
Posted by 横浜のtoshi at 2011年06月13日 21:58
at 2011年06月13日 21:58
 at 2011年06月13日 21:58
at 2011年06月13日 21:58to 横浜のtoshiさん
コメントありがとうございます。^^
確かに、強制的にさせられている受け身の勉強では、楽しめないですね。
義務教育中に学問を自ら楽しめる教育を受けることができたら、又違う人生もあるかもしれませんね。
私の場合は、それでもたどり着くのは建築だったかも・・・父の影響なので。^^;
次回は、建築ネタがベストですね。
前回、話したんですが、見事時間切れでした。
ネタを整理して、子どもたちにあう形を試しながら、回を重ねながら作っていきたいと思います。私のトレーニングのつもりで、気長に活動に参加していきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。^^
確かに、強制的にさせられている受け身の勉強では、楽しめないですね。
義務教育中に学問を自ら楽しめる教育を受けることができたら、又違う人生もあるかもしれませんね。
私の場合は、それでもたどり着くのは建築だったかも・・・父の影響なので。^^;
次回は、建築ネタがベストですね。
前回、話したんですが、見事時間切れでした。
ネタを整理して、子どもたちにあう形を試しながら、回を重ねながら作っていきたいと思います。私のトレーニングのつもりで、気長に活動に参加していきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
Posted by Shingo at 2011年06月14日 10:19










 はじめての方は、下記の記事からお読みになることをお勧めします。(^^)
はじめての方は、下記の記事からお読みになることをお勧めします。(^^)